鈴木清順監督作「ツィゴイネルワイゼン」
ユーロスペースで、「浪漫三部作」と称されている鈴木清順監督作の『ツィゴイネルワイゼン』『陽炎座』『夢二』をいっぺんに観て疲れました。
以下は『ツィゴイネルワイゼン』を分析したメモ帳の散文。
何か食ってるシーンが多かった。
食い物と食いたい物と食いたいけど食えない物と食えない物というようなベクトルの、なだらかなスペクトル。
生存という代謝とも言い換えられる営みに際して食事の当然であることと言ったら、まるで摂食以外の行為が全て異常であるかのようにさえ思えるほど。
うまそうだと思った次の瞬間、体外の何かの結実たる食物を歯で噛み砕いて台無しにしてしまった挙句、自律神経の手に渡して本人も忘れてしまう。
喉元過ぎれば、勝手に自分の血肉になる。
「ツィゴイネルワイゼン」の女たちは、焼かない前の人体から骨のみを取り出す方法として、血肉も魂も歯で刮ぎ舌で舐め取ってしまうのが適当だということをよく知っている。
欲することを当然のように体得している。
対して、青地と中砂は食うことにまともに直面する。
食い物以外も食い物と同じように飲み込んで消化してしまうということを知らない。舌を伸ばして捕まえて、自分にしてしまうという手法を持たない。
一度口に含んじゃうと知るのを極力避けていたかった具体的なことまでわかってしまうし、痛んでいたら腹を壊すリスクもあるし、ましてや噛むほど幻想も客観性もグズグズになっていく。
考え込んでしまえばしまうほど気後れする。
思慮が欲の実行を不味くする。
グチャグチャのものをなんも気にせず賞味してしまえればそれが甘美な現世利益だし、青地も中砂もそれくらいよく知っている。
それにしても女は生々しいものを涼しい顔で取り扱う。
ああやって平気で味わうことができたらいいのに、血肉に浸ると後が虚しい。恐ろしい。
だから行為の後に食べ残された骨に憧れる。
ひょっとすると死してなお血色を残した骨には、香りや味も少しは残っているかもしれない。
切実な情念は死を超越する色なのかもしれない。
あなたを骨の髄まで食い尽くさせてくださいと口にすることは彼らには難しいと見える。
それであればこそ真っ赤なカニに対する「死体食ったな」と言う呟きに羨望からの憎しみを感じる。
気持ち悪がって召し上がらないだろうけど、あの赤いカニを食べればきっと、生きている時の女からは得られなかった味がする。
別にカニバリズムという欲求があるのではなく、それは満たすことができる男性的肉欲への当てつけとして引っ立てられているのであり、言い換えれば架空の食欲による性欲の矮小化が見られる。
食欲と性欲の正常さにウンザリした後の、心にもない白いガイコツの交換。
しかし中砂がいくら狂人を身に纏ったところで、正常な女たちによる正常な欲には及びもつかない。
青地は焼かない前の死体からガイコツだけ残す方法を思いつくことができない。
中砂が性を厭うて青地を慕い、欲を厭うてガイコツを愛撫した結果がいまや誰の子なんだか本当にわからない豊子ならば、豊太郎・豊子がはじめから亡霊みたいだったのも至極当然な気がしてくる。
全て亡霊的男の亡霊的欲であるというような気がしてくる。
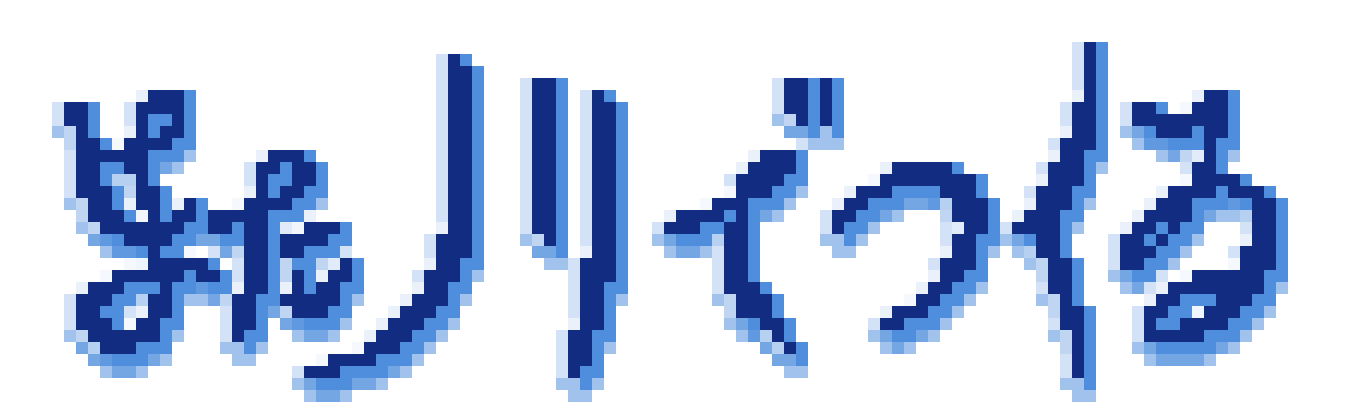



コメント