現在の個人的な存在観まとめ 常に書き終わらないので逐次更新です
現状こういう論考に耐えられるメンタルなので趣味で考えてます
基本的に2500年前と同じこと言ってる
パルメニデスとソシュールの影響
たぶん構造主義・相対主義寄り
存在論
存在するとはパルメニデスのいう通り「ない」のない「ある」である
様相でしかないけど、我々が何かと何かを他者と見做し峻別するための足掛かりとして、可能性と存在感の斑がある
何ものも実在として分けてあるものではないと同時に、程度の差こそあれ全て存在する
存在し、存在させる分析主体
人間に限定しない全ての事象について、存在するとは他者もしくは自信がそれと認識する可能性があることを意味する
青虫が被食者である自身を他のものと分けてこそ逃げ隠れする
そして小鳥もまた青虫や木の実を餌として認識したり、あるいは木の枝を休憩にふさわしい場所として認識することでそれぞれを存在者としてあらしめている
全ては自発的に、あるいは他者の認識よってその存在の強度を持っていて、人間が認識して記述したり言語化したりすることには特別な意味はない
分析者としての存在
分析は存在者が存在することの、我々に開示された側面であり、生物無生物に関わらず全ての事象が分析を含んでいる
相互の分析が、この世界の様相や構造を編むための関係なのである
①存在が内発的に他者と自信を峻別するならば、それはこの世界に存在するということが出来る
②他者の分析上に現れたものは存在するということが出来る
世界はその強弱(多寡≒濃淡)という斑のある場である
好き好んで言語化・定量化でもしない限り存在者(あるものの存在感)は輪郭を持たず、それである以上に厳密に検討することができない曖昧な擦り合わせと合意の結果として現れている
また、分析は存在するために利己的であるという偏向を持つ
あるものの斑
実体としてはもちろんのこと、想像にも言明による共有にものぼり得ない絶対無はない。
始まりがあったと仮定した場合、何かが「ある」ことを開始した時点でそれを保証する相対物としての無さえも唯一の「存在」に完膚なきまでに押しやられたはずであり、したがって「ない」はなく、存在は唯一である
最初の峻別以来、有無の分岐は起きていない。ここは、ある存在内の多寡の分岐の世界である。
可能性
程度の多寡とは何を意味し、それは「ない」の存在の力を借りずにあり得るのか
「ある:ない」の可能性ではなく、それは私たちの勝手な期待:失望/当為がそれぞれにあるという様相として斑を作っている
「架空の不在」としての「ない」は、個人的な想起あるいは言明にのぼる時点でポジティブな概念として微弱にある
「死すべき者どものドクサ」とは、私たちが生まれてから死ぬまでに認識する社会や言葉を含んだ人間の巣であり、そこには存在しないものなどない
認識とは全て分析であり、必ず判断を伴う
1か多か
人差し指と親指をくっつけた時に、再び離すことができるのは指と指の間に多分に何かが挟まっているからであり、厳密には接していないと考えられないだろうか
隣り合う、右手の人差し指の第一関節と第二関節は、少なくとも日本人にとってそれぞれに個別の名前を与えて峻別されることはなかった
それぞれの指を辿れば、指と指だったものは共に手であったばかりか、それを眺めていた両目共々、自分自身に帰されていく
そのように、別々の事象だと当然に思っている全てがそう見做しているだけの一つの存在なのだという理屈である
なぜ何もないのではなく、何かがあるのか
「なぜ」という問いは
・それを引き起こした(何かがあることを開始した)原因は何か
…因果の「果」としての説明
・それが引き起こされた目的は何か
…因果の「因」としての説明
を意味していることが多く、その根底には「事象の裏には意味や目的や原因があって然るべきだ」という謎めいたドクサがある
明確な始まりと終わりを全ての事象のうちに恣意的な線引きを以て見出すのはかなり特殊で偏った考え方である
農地に有目的に生える植物は私たちと親交が深いものであるが、それは全ての植物の中のほんの一部だ
思考の通時的計画性に基づく因果論は、古くは全ての植物は人間の糧となるべく作られたものであるという理屈を導き出したものだが、何かが自ら然るべく在ることに将来的な意味を期待する考え方を万物に敷衍する必然性はどこにあるんだろう
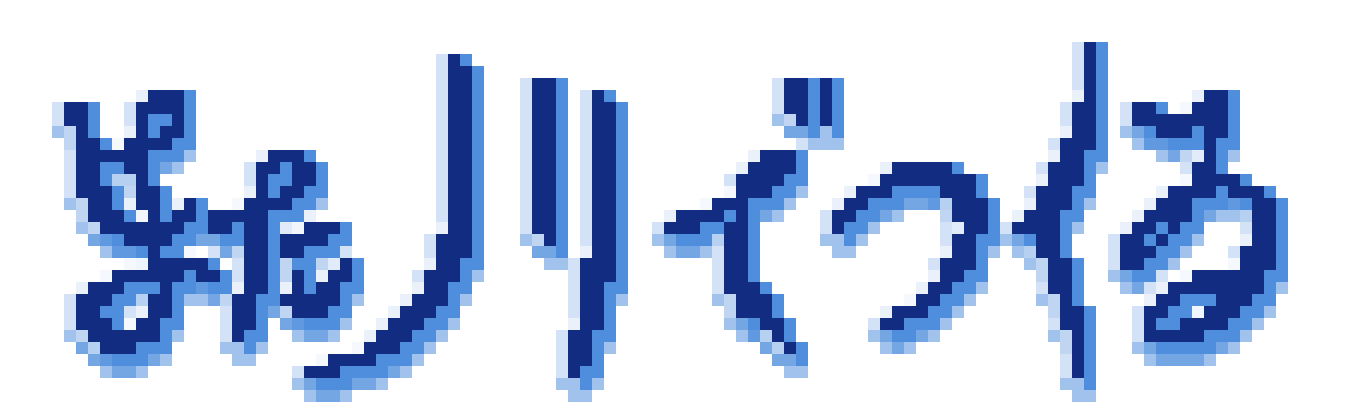
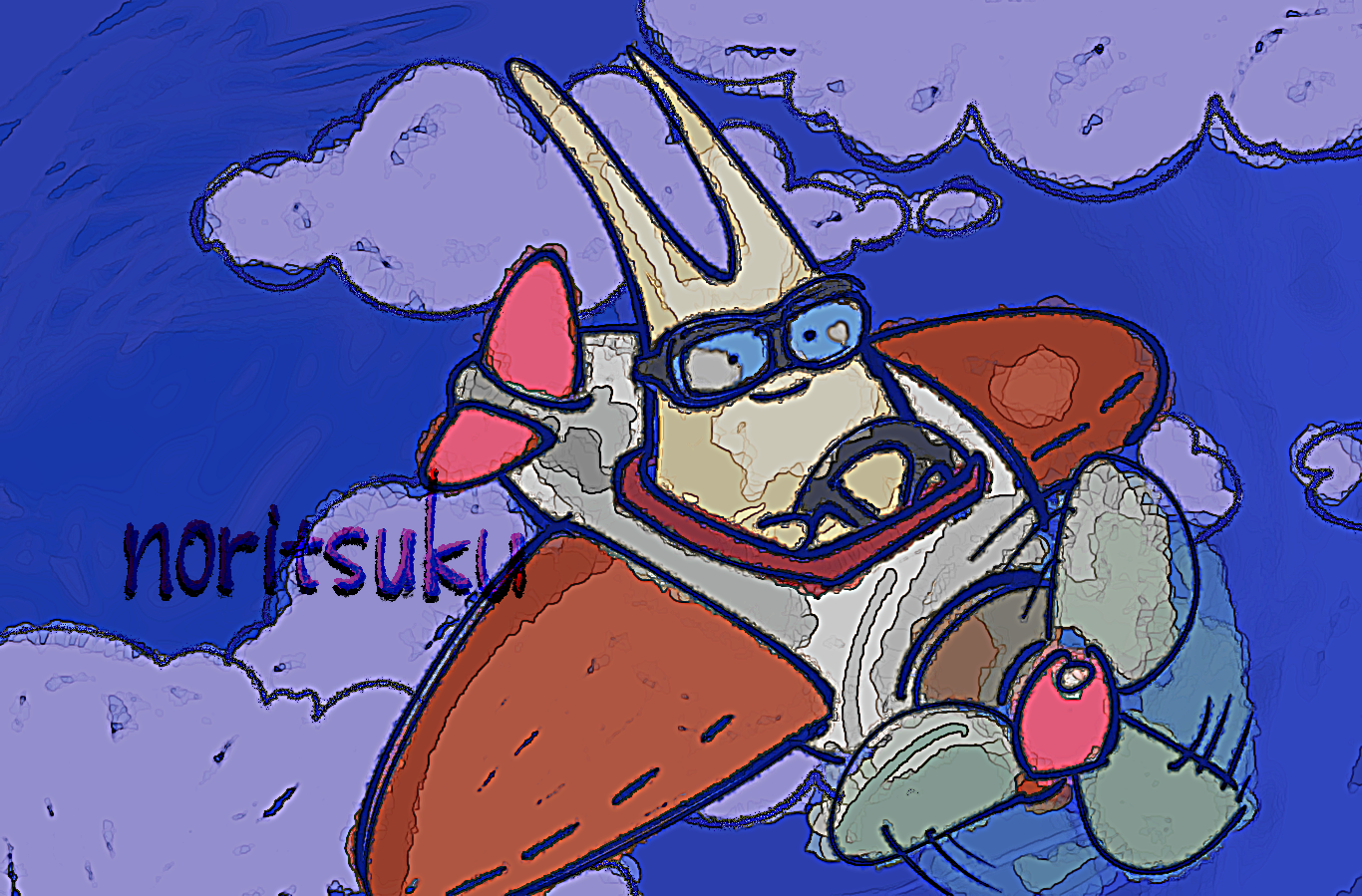

コメント